先日、LEDシーリングライトを本体ごと新規導入しました。
今まで使っていたシーリングライトはお役御免になりました。
さて、これをどう処分するか。
結果的には無事に処分できたのですが、なかなか大げさなことになったので、その手順をご紹介します。
作業が大変だったので、途中でほとんど写真を撮影できなかったのが悔やまれます。
※地域によって処分の仕方は様々だと思いますので、参考までにご覧ください!
スポンサードリンク
ゴミ出しのルール
僕が住んでいる糸島では、小型家電は「燃えないゴミの日」に出すことになっています。
燃えないゴミ専用の「黄色いゴミ袋」に入ればOKらしいです。
さて、今回処分したいシーリングライトは、「本体」と「カバー」の部分に分けられます。
蛍光灯を装着する「本体」の部分は、ゴミ袋に入りました。
だが、しかし。
問題はシーリングライトのカバー部分。
カバー部分との格闘
どう見てもカバー部分は大きすぎて、ゴミ袋には入りません。
そこで我が家では、カバー部分をカットして半分の大きさにすることにしました。
こうすればゴミ袋に入るサイズになります。
カットのために使ったのは金属をカットする用の糸ノコ。昔に何かの工作で使った糸ノコが、引き出しにしまってありました。
カバーはプラスチック樹脂なので、簡単に切れるだろうと軽い気持ちで望んだのですが、これが意外と分厚くてカットするのは一苦労。
一生懸命ギコギコやっても進むのは数センチ。
のこぎりも途中で引っかかり、スムーズには動いてくれません。
摩擦で変な匂いまでしてきます。
カバー全体の大きさは60cmくらいはあるので、この調子だと終わるまでにどれだけ時間がかかるのか……。
これ、結構たいへんなのでは……。暗雲がたちこめます。
作戦変更
このままではダメだ!
次に思いついた作戦がこちら。
「電動ドリルで点々と穴を開けていき、その間をのこぎりで切っていく」というのもの。
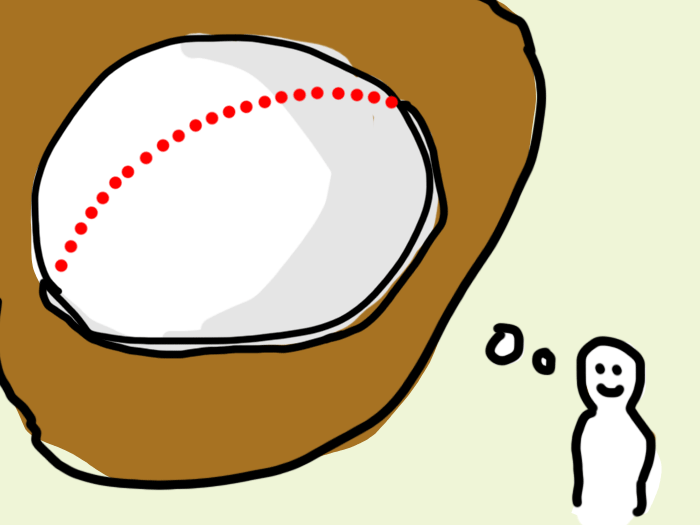
とりあえず電動ドリルを引っ張り出してきました。
我が家の愛用機はこちら。
RYOBIの電動ドリルです。
これ安くてかなり使えるので、一台あると便利です!
試しにドリルを使ってみると、思った以上にスムーズに穴が空きます。
おお。いい感じ。
とりあえずひたすら繰り返して、カバーの半分まで穴を開けました。
穴の数は15個くらいでしょうか。
ここで、妻からワイルドな提案。
妻「この時点で半分に割れないかな?」
私「いやーまだ難しいんじゃないかな? 結構厚いし。」
妻「いや、やってみる」
ベランダに持ち出して、両足でぐぐっと体重をかけていくと……。
パキィ!!
割れました!!!
ナイス判断!!!

この状態でゴミ袋に入れられたので、ミッションコンプリートです。
スポンサードリンク
おわりに:大きなものは持ち込む手もある
というわけで、燃えないゴミの日にシーリングライトを出すことができました。
よかったよかった!
ところで、今回は燃えないゴミ袋に入るサイズだったので良かったのですが、どうしても解体できないものは、粗大ゴミに出す必要があります。
ただ、粗大ごみ用の有料シールは540円もするし、業者さんへの予約も面倒くさい。
そこでオススメなのが、糸島の場合、クリーンセンターへ持ち込むこと。
平日しか受付できないのがネックですが、基本どんなものでも「10kgまで144円」で処分してくれます。
下記の記事にまとめてありますので、困っている方はぜひご覧ください。
→【糸島生活】粗大ゴミを個人持ち込み。糸島市クリーンセンターが便利。
この記事も読まれています

